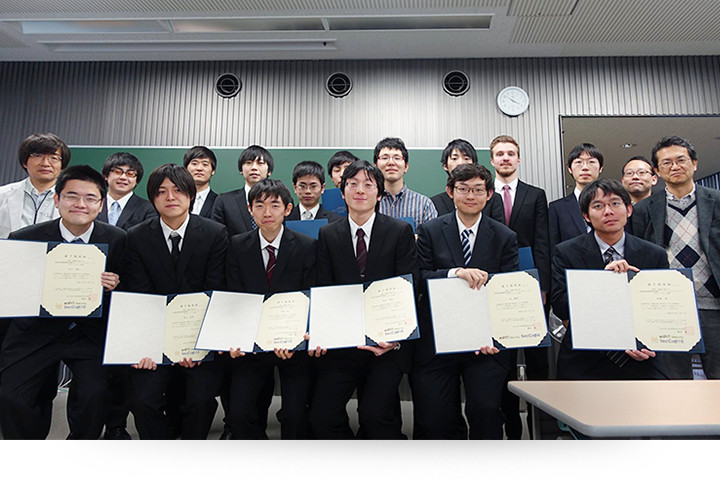これまでの取り組み(SecCapコース)

5連携大学(情報セキュリティ大学院大学、東北大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学、慶應義塾大学)が中心となり、社会・経済活動の根幹に関わる情報資産および情報流通のセキュリティ対策を、技術面・管理面で牽引できる実践リーダーの育成を目指します。本プログラムに参加し、共通科目2単位、演習2単位以上、先進科目2単位以上(または演習2単位でも可)、および基礎科目4単位以上の合計10単位以上を取得した学生にSecCap修了認定証を授与します。平成25年度は65名、平成26年度は88名の学生が、SecCap修了認定を取得しました。
平成26年度のSecCapコースのカリキュラムについては、セキュリティ分野のアドバイザー委員の方々にご視察いただいたほか、セキュリティ人材を求める企業や官公庁の方々にも紹介しました。
講義や演習の指導には、我が国トップレベルのセキュリティ関連組織・企業と専門家諸氏に協力いただくことができ、実際に起こっているインシデントの詳細な解説や、実データに基づいたセキュリティ分析演習は、受講生にとって大変貴重な機会であり、講義や演習後の受講アンケートでも高く評価されていました。
総じて、SecCapコースの講義と演習は、セキュリティ実践力の養成につながるものとして高く評価され、特に企業関係からは、SecCapコースの講義や演習を大学院生だけでなく、企業や官公庁へも提供して欲しいとの声が多く聞かれました。
SecCap修了生及び教員の活躍
幅広いセキュリティ分野の最新技術や知識をSecCap通じて習得した修了生も活躍しています。SecCap1期生である北陸先端科学技術大学院大学の伊藤竜馬さん、情報セキュリティ大学院大学の田中恭之さんは、SecCapコースで学んだ知見を自身の研究分野生かし、Workshop on Information Security Applications 2014、SafeConfig 2014 : Cyber Security Analytics and Automationにそれぞれの論文が採択されました。同じく1期生である慶應義塾大学の廣瀬雅治さん、野尻梢さんも日本ソフトウェア科学会 第31回大会において発表を行いました。また、トレンドマイクロ プログラミングコンテストにおいて東京大学の平原秀一さん、寺尾拓さんが数ある難関を突破し、それぞれ3位と7位に入賞しました。さらに、SecCapコースの教員の取り組みも評価され、北陸先端科学技術大学院大学の宮地充子教授が「科学技術分野の文部科学大臣表彰 研究部門 科学技術賞」を受賞すると共に奈良先端科学技術大学院大学の猪俣敦夫准教授(現在、東京電機大学教授)が(ISC)2において「アジア・パシフィックISLA」を受賞しました。

広報活動及び国際連携の計画
また、SecCapコースの教育成果を本コースに関連する企業や研究者が参加する国際会議や国内学会で発表し、アピールを行いました。さらに、セキュリティに関する先進的な実践講義を行っている海外の大学(ベルギー、フランスなど)の演習教材、講義資料、演習の実施形態などの教育知見を授業の見学及び教員間のディスカッションを通じて習得し、演習科目の一層の充実を図る計画を進めています。
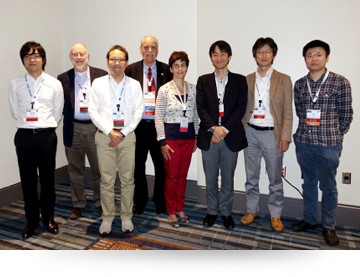
東北大学における実施体制
東北大学では、ハイブリッド人材への先行取組みとして東北学院大学工学部、宮城大学、東北工業大学、仙台高等専門学校が平成26年度の参加校として、本SecCapコースに参加。実践演習として開講する「ハードウェアセキュリティ演習」の教材開発は産業技術総合研究所と共同で実施しました。また、教材のパッケージ化を行い連携校(奈良先端科学技術大学院大学)に提供を行いました。さらに、株式会社仙台ソフトウェアセンター(NAViS)を通じて、仙台地域における技術系の高度人材育成・定着を目指した産学官コンソーシアム(Sendai Schemeコンソーシアム)の枠組みを用い、 株式会社サイバー・ソリューションズより支援を受けて、ネットワークセキュリティ実践(PBL演習)を実施しました。
平成26年度は17名(平成25年度の2倍以上)の学生が修了認定、うち6名は情報セキュリティ・スベシャリスト認定の「SecCap10」を取得しました。